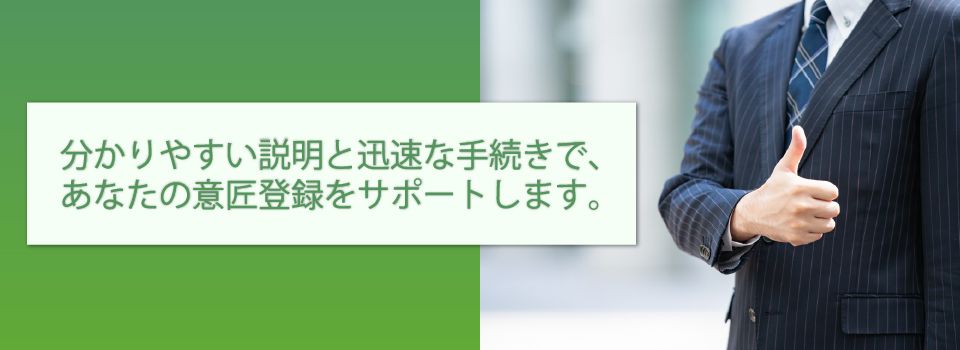意匠法の保護対象と「意匠」の定義
意匠法では、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としています(1条)。
この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様もしくは色彩、またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもののことをいいます(2条1項)。ここで「美感」とは、美に関する感覚のことをいい、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、視覚を通じて何らかの美感を起こすものであれば足ります。
分かりやすく言えば、意匠とはデザインのことであると考えていただいて良いでしょう。では、あなたが創作したデザインが、意匠として認められるかどうかを確認していきましょう。
- ◎ 物品と認められるものであること
-
- 不動産は、物品とは認められません。
- 電気、熱、光、気体、液体などは、物品とは認められません。
- ◎ 物品自体の形状であること
-
- 不動産は、物品とは認められません。
- 販売展示効果を目的として、ハンカチを結んでできた花の形状。
- ◎ 視覚に訴えるものであること
-
- 微細であるために肉眼によってはその形状を認識できないもの。
※ ただし、取引に際して拡大して観察するのが通常である場合には、物品に該当します。
- ◎ 視覚を通じて美感を起こさせるものであること
-
- 機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの。
- 意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけのもの。
意匠登録の要件(3条)
- ◎ 工業上利用することができる意匠であること(3条1項柱書)
-
- 自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの。
- 土地建物などの不動産。
- 純粋美術の分野に属する著作物。
※ 「工業上利用することができる」とは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産できるということであり、現実に工業上利用されていることは要しません。
- ◎ 新規性を有すること(3条1項各号)
-
- 出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠。
- 出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠。
- 出願前に日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠。
- 上記のものに類似する意匠。
- ◎ 創作非容易性の要件(3条2項)
-
- 出願前に、その意匠の属する分野における通常の知識を有するものが、日本国内又は外国において公然知られた形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものは、意匠登録を受けることができません。
容易に創作ができるものとされる意匠の例
- 置換の意匠。
- 単なる寄せ集めの意匠。
- 配置の変更による意匠。
- 構成比率の変更または連続する単位の数の増減による意匠。
- 公然知られた形状等をほとんどそのまま表したに過ぎない意匠。
- 商慣行上の転用による意匠。